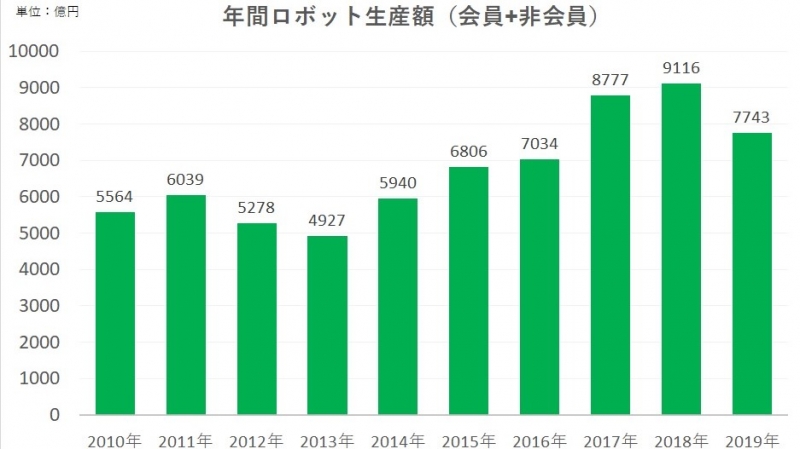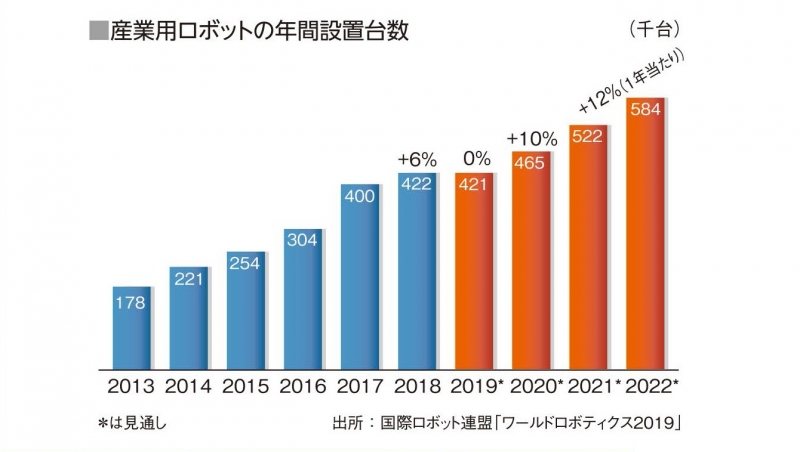「チェルシー」設立、産学でロボット人材育成/経済産業省
経済産業省の主導の下、産学連携でロボット関連の人材を育成する組織「未来ロボティクスエンジニア育成協議会」(略称はCHERSI<チェルシー>)が2020年6月24日、正式に設立された。19年12月に東京都内で開かれた「2019国際ロボット展」で、同省とロボットメーカーなどがチェルシー設立の覚書を交わし、設立に向けて準備を進めてきた。「ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会」の下にチェルシーの事務局を置き、ロボット人材育成のためのさまざまな活動に取り組む。