
[気鋭のロボット研究者vol.25] 減速機が変わると、ロボットも変わる【後編】/横浜国立大学 藤本康孝教授
藤本康孝教授などが開発した「バイラテラル・ドライブ・ギヤ」は、前編で紹介した協働ロボット向けの用途だけでなく、さまざまな応用の可能性を秘める。藤本教授は「自律して行動を決める知能ロボットの研究に貢献し、環境にやさしいロボットの開発もできる」と期待を込める。
生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン
NEW ARTICLE

藤本康孝教授などが開発した「バイラテラル・ドライブ・ギヤ」は、前編で紹介した協働ロボット向けの用途だけでなく、さまざまな応用の可能性を秘める。藤本教授は「自律して行動を決める知能ロボットの研究に貢献し、環境にやさしいロボットの開発もできる」と期待を込める。

宇宙作業用ロボットを開発するベンチャー企業のGITAI(ギタイ、東京都大田区、中ノ瀬翔最高経営責任者)は7月12日、米国民間企業のナノラックスと共同で、2023年に宇宙船外環境での自律ロボットによる技術実証を行うと発表した。

東京工業大学発のベンチャー企業ハイボット(東京都品川区、ミケレ・グアラニエリ社長)は7月12日、多関節ロボットアーム「Float Arm(フロートアーム)」で施設の点検サービスを実施したと発表した。点検したのは三井化学大阪工場の施設で、同製品で国内施設を点検したのは今回が初めて。

ロボット業界のフロントランナーが顔をそろえたスペシャルセッションは来場者の関心が高く、立ち見客も多くいた。登壇者自身にとっても業界の動向を知る機会であり、他の登壇者の発言時にメモを取る様子も見られた。「これからのロボットの使い方」とのメインテーマに基づく3つのお題のうち、後編では「ロボットの活用領域は広がる?」と「未来に向けたロードマップ」について、登壇者それぞれの主張を要約して紹介する。

3日間で合計4万1880人の来場者を集めた「ロボットテクノロジージャパン(RTJ)2022」。会場では連日、そこかしこで製品や技術がPRされたが、とりわけ多くの来場者の関心を集めたのが、会期初日の6月30日に開催された主催者企画「スペシャルセッション」だ。ファナックや安川電機、デンソーウェーブ、ABBの大手ロボットメーカー4社の幹部が参加。「これからのロボットの使い方」をメインテーマに、それぞれのロボットメーカーが思い描く未来像を語った。
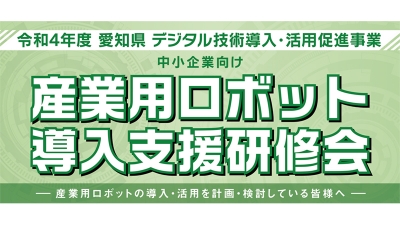
愛知県と名古屋工業大学の産学官金連携機構(機構長・江龍修同大学副学長、※編集部注:金は金融機関)は産業用ロボット導入を検討する県内の中小企業を対象に、2022年9月9日から翌23年1月20日にかけて「産業用ロボット導入支援研修会」を開催する。

ドイツに本部を置く国際ロボット連盟(IFR)は6月28日、新会長にABBのマリーナ・ビル氏、新副会長にファナックの山口賢治社長を選出したと発表した。ビル氏はABBのロボティクス事業のグローバルマーケティング&セールス部門を統括し、同分野で25年以上の経験を持つ。ビル氏は「IFRを会長として率い、業界に奉仕することを光栄に思う。IFRのメンバーの信頼と支援に感謝する」とのコメントを発表した。
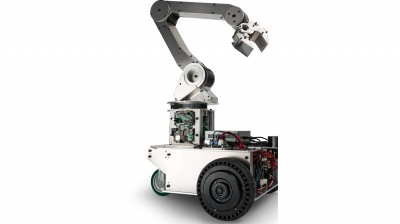
研究開発用の台車ロボットなどを製造、販売するヴイストン(大阪市西淀川区、大和信夫社長)は7月1日、ロボットアーム「AMIR 740」を発売すると発表した。

さがみはら産業創造センター(相模原市緑区、橋元雅敏社長)が運営する「さがみはらロボット導入支援センター」は6月30日、「第6期 ロボットSIer養成講座」の募集を開始した。

昨年、米国のマネジメントサイエンス誌にある論文が掲載された。「The Robot Revolution: Managerial and Employment Consequences for Firms」(ジェイ・ディクソン、ブライアン・ホン、リン・ウーによる共著)、無理矢理日本語に訳せば「ロボット革命:企業における経営と雇用の帰結」といったところか。1990年代半ばから20年分ほどのカナダ統計局の公開データを使い、ロボットの導入と雇用の関係を分析した力作である。